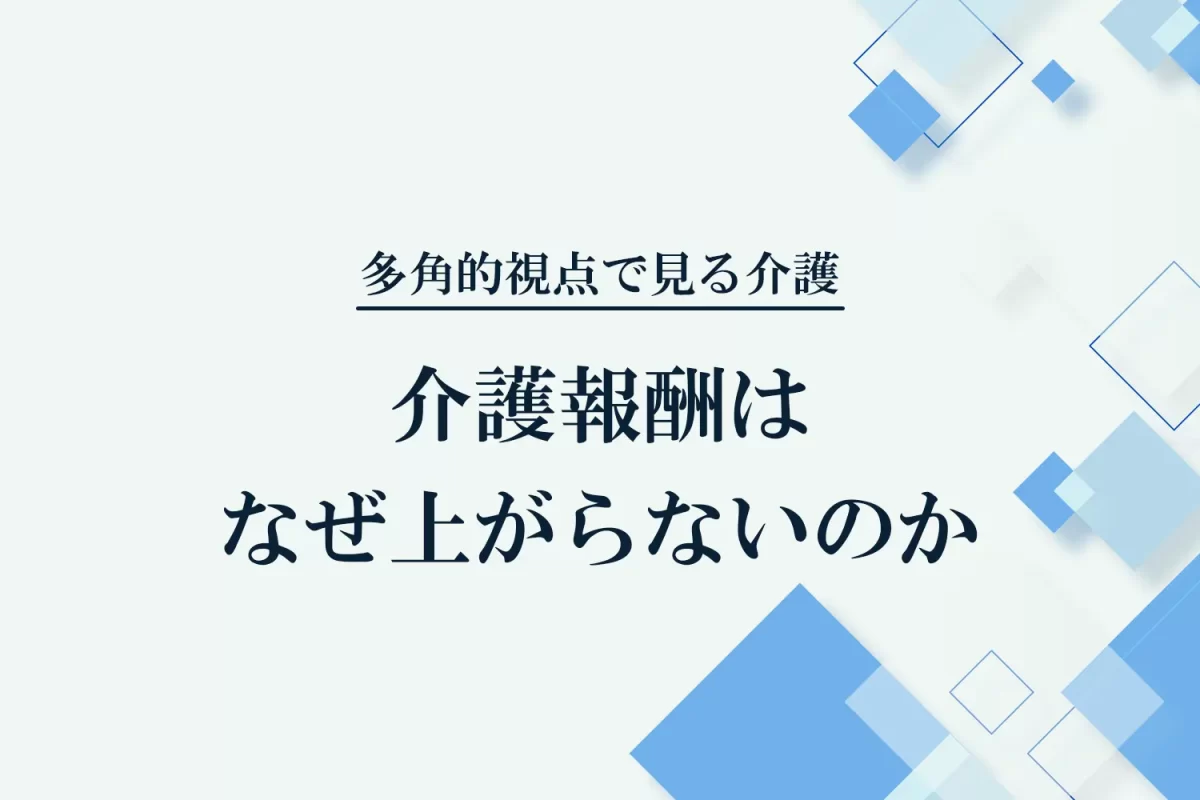介護報酬はなぜ上がらないのか?
財務省の「財務に関する資料」によりますと、わが国の令和6年度末の普通国債累積残高は1061兆円と見込まれています。
出典:財務省Webサイト「財政に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm
国際的には国債残高は対GDP比で比較されますが、2024年のIMFの資料によりますと、日本は世界の178か国中257.2%の178位であり、177位のギリシヤ179.5%よりも78ポイント多い状況にあります。
累積国債を減らすためには・・・
この累積国債を減らすためには、歳入を増やすか歳出を減らすしか方法はなく、歳入を増やすには、増税するか経済成長を促し税の自然増に繋げるしかなく、歳出を減らすには緊縮財政で国債の発行を抑えるかしかありません。
現在、政府はできるだけ増税を回避しつつ、経済成長による税収の自然増を期待しながら、現実的には緊縮財政の体制をとっています。さらに云えば、その抑えられた歳出の中での予算組みは、こちらを増やせばあちらが減るという予算の奪い合いであり、必要度合いが他分野よりも高いことをアピールしていかなければ、必要だから予算を付けるということにはならないのです。
その中でも社会保障費は歳出項目の中で最も多くの比率を占めていて、如何に社会保障費を抑制するかが注目されています。
緊縮財政派と積極財政派
国会議員の中でも、このような考え方は「財政健全化」を目標とした「緊縮財政派」と呼ばれており、反対に国債発行してでも財政を拡大していくべきだという「積極財政派」と大きく二派に分かれています。岸田前総理、石破総理、野田民主党党首は前者であり、故安倍元総理、高市早苗衆議院議員、西田昌司参議院議員、原口一博衆議院議員は後者になります。 積極財政派の主張は、国債残高はその半分は日本銀行が保有していて、日銀に払われる金利も必要経費を除いて余れば国庫に戻るし、累積国債は60年で償還するというルールは世界的に日本にしかない等の説明を行い、まずは国債発行で経済を成長させて国民生活を安定させるべきというものです。
この両派の主張については本題ではありませんので詳細には説明しませんが、介護報酬が上がらない根底には国家財政の問題があり、与党の中でも野党の中でも意見統一がされていないということと、仮に積極財政派の主張のように国債発行がされたとしても、それは経済発展などに向けられがちであり、すぐに社会保障の充実には結び付かないと思われます。
政府の方針がこのような状況にあることが、介護報酬が上がらない理由ですが、他の視点からも考察しますと、つぎの3つの原因も考えられます。
- 社会保障費の増大と財政的な制約
- 高齢者数の増加と国民のコンセンサス
- 経済成長の停滞と賃金の引上げ
1.社会保障費の増大と財政的な制約
社会保障費の増加
日本は急速な少子化と高齢化が進む中で社会保障費が年々増加しています。この増加は歳出に大きく影響を及ぼしていて、介護報酬を抑制する要因となっています。
令和に入ってからの予算ベースでの歳出と社会保障費の推移を表にしました。また介護給付費については、その1/4が国費なのでその額を算出しています。

出典:財務省Webサイト「平成31年度一般会計予算,p.83,p.397」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf
出典:財務省Webサイト「令和2年度一般会計予算,p.80,p.247」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2020/dlpdf/DL202011001.pdf
出典:財務省Webサイト「令和3年度一般会計予算,p.82,p.245」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2021/dlpdf/DL202111001.pdf
出典:財務省Webサイト「令和4年度一般会計予算,p.82,p.239」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2022/dlpdf/DL202211001.pdf
出典:財務省Webサイト「令和5年度一般会計予算,p.82,p.249」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2023/dlpdf/DL202311001.pdf
出典:財務省Webサイト「令和6年度一般会計予算,p.85,p.263」
https://www.bb.mof.go.jp/server/2024/dlpdf/DL202411001.pdf
この表から見えてくることは、令和元年度から6年度までの6年間で、歳出総額に占める社会保障費の割合が33~35%で推移していて、実質的にはこのラインがアッパーとなっている。
6年間で歳出総額が1.11倍になっているのに対して、社会保障費は同様に1.11倍ですが、介護給付費国費負担分は1.16倍に増加し、社会保障費に対する比率も6年間で9.4%から9.9%まで約0.5ポイント上がっています。
増加する社会保障費を歳出の33%程度で押さえている中で、介護給付費は(社会保障費の10%以下ではありますが)じわじわとその額も比率も上げてきていることになります。
歳出総額に大きな伸びが無いということは、財政的に制約がかかっているということで、その中でも必要とされる社会保障費は伸びてきているという状況が見えます。

出典:総務省統計局「財政に関する資料」
https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf
財務省は平成30年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針2021)」を受けて、2020年度に向けて社会保障関係費の実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びに抑えることを目指す」としています。
この「高齢化による増加分」とは、高齢者数の伸びと年金スライド分から構成されているとのことですが、高齢者の伸び分だけを見ると、令和元年度から6年度までの高齢者人口の増加率は1.02倍なので、1.02倍を目指しつつ1.11倍に落ち着いていると読み取れます。
このことから、財政的な制約のある状況で社会保障費の増加分をギリギリ抑え込んでいるということ。また介護給付費に係る国費負担は社会保障費の中では比率的には少ないものの、伸び率は高く警戒しなければならないのです。
2.高齢者数の増加と国民のコンセンサス
高齢者人口と社会保障費の増加
第1次ベビーブーマー世代が65歳以上になったことから、高齢者人口は増え続けています。
就労可能な若年者数の増加は、生産量の増加に繋がり、消費の増加にも繋がることで税収は増加し、社会保障費を使うことは少なく、歳入が増え歳出における社会保障費は抑えられます。
一方で、高齢者数の増加は、生産量の増加にも消費の増加にも繋がらず税収は伸びず、年金、医療、介護に関する費用はかかってきます。歳入は増えずに歳出における社会保障費が増えていきます。
高齢者の増加とともに少子化も問題になっています。国からみれば、高齢者が増加して使う額(社会保障費)が増えていき、少子化が進み生産年齢人口が減ることで稼ぐ額(税金、社会保険料など)が減っていくという今の状態は、財政危機へと進んでいるように見えるのです。
そこで次に国民の視点から、高齢者に社会保障費がかかり財政を圧迫している状況はどう見えるのでしょうか。
シルバー民主主義と世代間格差
シルバー民主主義という言葉があります。選挙権をもち選挙に行く高齢者が多いと、議員は選挙に勝つために高齢者に有利な政策を主張したり、その方向に向かっていくという考え方です。
また、世代間格差という言葉もメディアでは多く使われています。国の歳出において社会保障費が伸びていて、そちらにばかり使われているので若い層には予算が回っていかない。今の高齢者は十分な年金がもらえるのに、若い層には年金が枯渇してもらえないかもしれない。といった主張です。
実際に使われている金額からすればその通りなのですが、人口構造を無視して社会保障費を削減すれば生存できない高齢者も出てくることと思います。
そもそも年金の話でいえば、日本の年金制度は賦課方式をとっていて、将来に向けて積立運用していますし、物価スライド方式からマクロ経済スライド方式に変更され、物価や賃金が上昇しても、その上昇率は一定割合(スライド調整率)だけ抑える仕組みになっています。
しかし、シルバー民主主義や世代間格差の話はマスコミでも取り上げられ、社会保障費を減額すべきだという声も多く、介護報酬を上げることへの国民のコンセンサスが得られているとは言えない状況にあります。
- 賦課方式 : 現役世代が支払う保険料をその時の年金受給者に給付する方式
- 積立方式 : 加入者が支払った保険料を個人ごとに積み立て、将来自分が受給する際に使用する方式
- 修正積立方式 : 現在の保険料収入で年金受給者に給付しつつ、一部を積み立てて運用する方式(年金積立金管理運用団体(GPIF)が管理・運用しており、その運用資産は2024年9月末で役248兆2274億円。また2001年から2024年9月末までの累積収益額は約153兆6431億円になります)
3.経済成長の停滞と賃金の引上げ
日本の経済
日本の経済は1985年のプラザ合意【アメリカの貿易赤字(特に対日貿易赤字)を是正するため、アメリカ、日本、西ドイツ、フランス、イギリスの間の各国で為替介入を行い、ドル売り円買いを促進して円高を促進した】、1986年の第1次半導体協定【アメリカが日本の半導体産業の急成長による市場独占や安い価格を問題視し、日本の半導体市場を外国企業に開放させ、日本の半導体の高値設定、関税制裁などを課した】の二つの大きな出来事を境に、急激な円高(1ドル=240円から約2年で120円台)になったことで自動車など輸出産業が打撃を受け、半導体分野においてはシェアが低下し、アメリカのインテルや韓国のサムソンが台頭しました。
このように経済成長は抑制されてしまったため、日銀は1986年低金利政策をという金融緩和を行ったが、逆に行先を失った資金は土地や株式に投機という形で流れていきバブル時代を形成しました。
失われた30年
しかしその後、日銀はバブルの過熱を抑えるため金融引き締めに取り組み、株価は暴落し地価は下落した。その結果1997年から銀行や証券会社が倒産するという金融危機を迎えることとなりました。
ここから日本経済は「失われた30年」と呼ばれる長期経済停滞に入り、現在に至っている。
ここにきてコストアップ型のインフレが起こり、デフレ時代からの脱却と言われているが、実質賃金は上がっておらず、報道先行の状況にあると考えられます。
デフレからの脱却を目指す方策として、政府も連合なども賃金アップを目指していますが、介護報酬を主たる収入としている私たちの業界では、3年に一度の報酬改定を待たねばならず、またその上昇額から考えると、十分な金額が得られるとは考えにくい状況にあります。
介護報酬が上がる要素が見つからず、歳出の中で社会保障費を増やすためには何かを削らなければならず、社会保障費の額が決まってもその中で予算の奪い合いがあり、介護報酬が上がれば何かの報酬が下がる(今までは薬価が下がってきました)、そして介護報酬の中で何かが上がれば何かが下がる(今回の改定では特養、老健の報酬が上がりましたが、訪問介護の報酬が落ちました)という状況の中では、国に期待するのではなく、いかに生き残るかを考えなければならない時代になってきています。
この記事の執筆者

江頭 瑞穗
神奈川県出身 1987年設立の学校法人国際学園横浜国際福祉専門学校にて、介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事(任用)、保育士、幼稚園教諭などの養成を行う学科、コースの設立を主導し、事務長、事務局長を経て1991年理事長に就任。1995年同職を辞し、学校法人、社会福祉法人のコンサルタント業務を開業。翌1996年 株式会社日本アメニティライフ協会を設立し、グループホームケアの実践を行うと共に、神奈川県、東京都に限定した介護事業を展開。現在、子会社にて日本語学校を経営するとともに、社会福祉法人理事として特別養護老人ホーム、老人保健施設、また医療法人理事としてクリニックの経営に携っている。