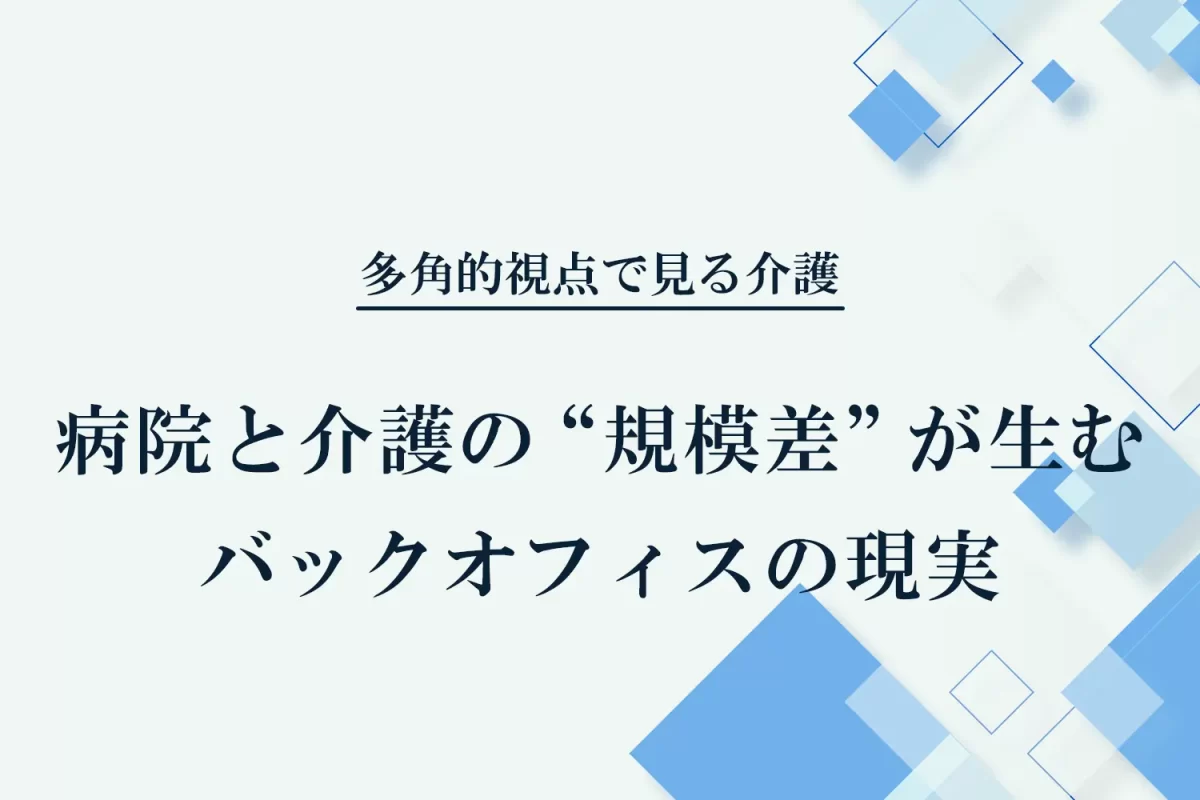病院と介護の“規模差”が生むバックオフィスの現実
〜単独経営が難しくなる時代へ〜
先日、ある地域の特養を訪問した際のことです。
夕方19時を過ぎても、事務所の明かりだけがぽつんと灯り、静まり返った廊下の奥から、ようやく施設長が戻ってきました。日中は現場の巡回、家族との面談、急な相談対応が立て続けに入り、結局一度も自席に座れなかったそうです。
「今日こそ、溜まりに溜まった書類の整理まで進めたかったんですけどね…」
そう言って手にしていたのは、午前中のうちに届いたはずの書類束。そこには職員の勤怠変更の確認、契約書の更新、行政への報告書の下書き、研修の出欠表、備品購入の稟議、家族向けのお知らせ文書など、大小さまざまな“未処理”の仕事が混ざり合っていました。
そのひとつひとつを確認していくにも、内容を確かめ、関連する資料を探し、職員へ確認し、最終的に押印や提出の段取りを整える必要があります。しかし、電話が鳴れば応対し、職員から相談が入れば時間を取られる。結局、書類の束にはほとんど手がつけられないまま時間だけが過ぎていきます。
「日中はどうしても現場が最優先になりますしね…書類は夜に回すしかないんです」
施設長はそう言って笑いましたが、その表情はどこか疲れ切っていました。
この姿は決して特別ではありません。むしろ、介護の現場では“日中は机に座れない”ことが当たり前になっている職場も多く、本来は日中に行うべき管理業務が、早朝・夜間に圧縮されてしまうケースが数えきれないほどあります。
一方、病院に足を運ぶと、総務、経理、人事、医事課、地域連携室、情報システム部といった部署が整然と並び、業務が分担されている光景を目にします。外から見ると「事務職が多くて羨ましい」と映るかもしれません。
しかし、実際の病院事務も余裕があるとは言い難く、むしろ医療制度改定、行政対応、監査準備、電子カルテの運用、医療安全対策、感染管理……と、増え続けるタスクが職員の時間を奪い続けています。病院は“人が多い”わけではなく、“制度が人を必要とする構造”になっているのです。
ただ、そのうえでやはり強調したいのは——
介護のバックオフィスは、病院以上に“構造的に回りにくい仕組み”のまま運営されているという事実です。その理由を、数字と現場の実態をもとに、あらためて整理してみたいと思います。
病院の7割が中小規模。それでも“ 部署が成立する ”理由
日本の病院は約8,000。このうち約70%が200床未満という事実は意外に知られていません。つまり私たちが「病院」と聞いて思い浮かべる大規模医療機関はむしろ少数派で、実態は地域の中小病院が日本の医療を支えているのです。ですが、50床規模であっても病院のバックオフィスは“部署として成立”します。
なぜか。
医療に求められる事務機能は、小規模であっても決して減らないからです。
- 診療報酬請求
- 医療法に基づく年間40〜50種の管理対応
- 看護配置、人員配置、届け出
- 医療安全管理、感染症対策
- 地域連携、退院調整
- 情報システム管理
- 経理・財務・給与・勤怠管理
- 人事労務、研修企画
これらは病床数が50であれ100であれ「やらないといけない仕事」です。むしろ病床規模が小さいほど、
病院のバックオフィス体制(規模別イメージ)
|
病床規模 |
医事課以外の |
医事課 |
合計 |
|
50床 |
5〜6名 |
5〜7名 |
10〜13名 |
|
100床 |
8〜12名 |
8〜12名 |
16〜25名 |
|
200床 |
10〜20名 |
15〜20名 |
25〜40名 |
50しか病床数がないにも関わらず、医事課以外のバックオフィス“だけ”で5〜6名というのは、介護事業所から見ると驚きかもしれません。しかし病院では、これでも「ギリギリの人数」です。実際、各部署の担当者は日々膨大な情報を扱います。
総務は行政通知やガイドラインに目を通し、年間数十件に及ぶ届け出や報告書を作成します。人事は職員の休職・復職、研修計画、採用日程を調整し、経理は膨大な請求書・予算管理に追われます。医事は毎月数万枚単位のレセプトを処理し、システム担当は電子カルテのアップデート、トラブル対応、院内ネットワーク整備などを担います。
病院は人数こそいるものの、業務量は常に飽和に近く、DXが進んでも“仕事が減る感覚”にはまだ遠いのが現状です。ただし、ここ数年、確実に変化があります。
病院のバックオフィスDXが本格的に動き出した
- 会議録音 → AIが議事録化
- 文書作成 → 生成AIが一次原稿を作成
- レセプトチェック → AIが過去データと照合
- 看護記録 → 音声入力で半自動化
- 苦情・事故報告 → システム化で標準化
- 採用広報 → AIで原稿作成・分析
病院は複雑な業務量に押されながらも、DXができる“規模と体制”が整ってきています。
介護は“小規模事業所”が圧倒多数。バックオフィスは“ 個人戦 ”
では、介護はどうか。数字を見れば一目瞭然です。
| 有料老人ホーム | 約13,000 |
| グループホーム | 約13,000 |
| 特養 | 約9,000 |
というように、介護施設の数は病院の比ではありません。数字だけを見ると「巨大な産業」に感じられますが、その内実は大きく異なります。介護施設の多くは、規模が小さく、全国各地に細かく点在しています。つまり “事業所数は多いが、1施設あたりは極めて小規模” という構造です。これは、事業所単位での事務処理が“構造的に重くなる背景”ともいえます。
では、そのバックオフィスの実態はどうか。代表的な施設で見ていくと、次のようになります。
介護施設のバックオフィス体制(代表例)
|
施設種類 |
規模 |
バックオフィス |
|
特養 |
100名規模 |
1〜3名 |
|
老健 |
100名規模 |
2〜4名(+医事2〜4名) |
|
デイサービス |
20〜40名 |
0〜1名(専任なし多数) |
驚くべきは、特養の100名規模であっても“事務は1〜3名”。100名の利用者、60〜80名の職員を抱える中で、この人数です。その数名が担う業務は、病院のバックオフィスと大差ありません。
- 要件管理
- 介護請求
- 行政報告
- 入退所調整
- 職員の勤怠・給与
- 採用・面接日程調整
- 家族対応
- 経理の一次処理
- 研修計画
- 会議運営
- 広報
- 安全管理
病院では“部署単位”で担うものを、介護ではほぼ1〜2名で担うのです。施設長が現場と事務の両方を抱え込み、夕方にしかデスクに戻れないのは、この構造が原因です。しかも、介護は病院のように情報システム部があるわけでもありません。記録様式ひとつ直すにも、職員同士で相談しながら手作業で修正し、周知し、紙で配布し、回収します。現場に任せざるを得ない環境が続いてきたことで、業務の統一も進みにくい状況があります。
病院も大変。でも介護は“ 構造的にもっと厳しい ”
病院は人数こそ多いものの、業務の専門性や責任の重さから、事務も常に緊張感を持って仕事をしています。DXも進んでいますが、制度改定の頻度と複雑さから、改善が追いついていない側面もあります。一方、介護は人数が少ないうえに、制度も複雑化し、行政対応も増え、採用難も深刻化しています。しかし、その状況に見合うバックオフィス体制にはなっていません。つまり、
| 病院 | 人数は多いが仕事も多い。DXで改善の余地がある。 |
| 介護 | 人数が少なく仕事は増え続ける。構造的に“改善できる余地”が少ない。 |
この違いが、両者の事務負担を大きく分けています。
なぜ介護はここまで追い詰められているのか?
介護保険制度が始まった2000年頃、国が想定していた介護事業所の姿は、「地域の小さな事業所が、家庭的なケアを提供する」というものでした。そのため、制度設計は“小規模向け”になっていました。
しかし現実は、
- 利用者数の増加
- 医療ニーズの高度化
- 認知症ケアの専門性
- 加算の細分化
- 記録の義務化
- 介護事故・苦情への社会的関心の高まり
- 職員の採用難
- ICT対応の必須化
など、想定を遥かに超える状況になっています。制度は“大規模化・高度化”しているのに、事業所は“小規模設計”のまま。ここに大きな歪みが生まれています。
これから介護は「単独経営」では戦えない
私は、今の介護経営が抱える課題の本質は、“事業所ごとの管理”を前提にしている点にあると考えています。これからの介護は、次の方向へ進む必要があります。
① バックオフィスを“法人本部”に集約する
採用・経理・総務・研修・加算管理・DXなど事業所単位ではなく、法人全体で担う仕組みが必要です。
② “紙の業務”を減らし、DXを進める
まずは
- 記録
- 勤怠
- 加算管理
- 会議議事録
- 家族連絡
など、改善しやすい部分から始めることが重要です。
③ 事業所同士で“共同化”していく
法人内でなくとも、地域で
- 研修共有
- 採用共有
- ICT共有
などの連携が必要になっていきます。
特に①は、現場の負担を劇的に軽減します。
おわりに
病院も介護も、バックオフィスが楽なわけではありません。ただ、その成り立ちと歴史から、
病院は“部署として組織をつくれる”のに対し、介護は“個人でなんとか回す”構造になってしまっています。これは、現場の努力ではどうにもならない領域です。だからこそ、介護経営はここから大きく転換していく必要があります。
「事業所で抱え込む」から
「法人で支える、地域で支える」へ。
この方向性を考え始めることが、これからの介護事業の持続性を守る第一歩になると感じています。
この記事の執筆者

事務長さぽーと株式会社
代表取締役 加藤隆之
医療法人おひさま会 事務局長・理事、中小企業診断士、MBA
病院向け専門コンサルティング会社にて全国の急性期病院での経営改善に従事。その後、専門病院の立ち上げを行う医療法人に事務長として参画、院内運営体制の確立、病院ブランドの育成に貢献。M&A仲介会社(日本M&Aセンター上席研究員)を経て起業。現在は、病院・企業の経営支援の傍ら、アクティブに活躍する病院事務職の育成を目指して各種勉強会の企画・講演・執筆活動など行っている。共著に「事例でまなぶ病院経営 中小病院事務長塾」「事例でまなぶ病院経営 事務管理職のすすめ」がある。